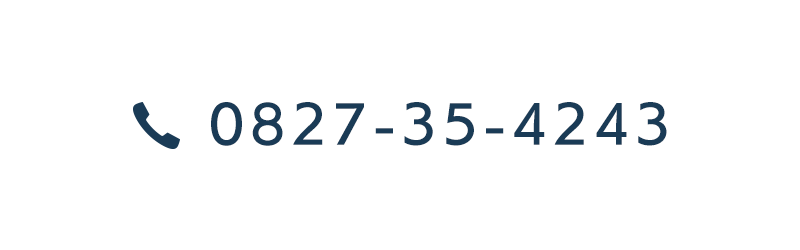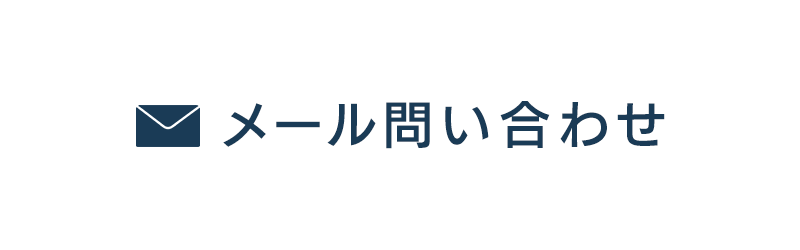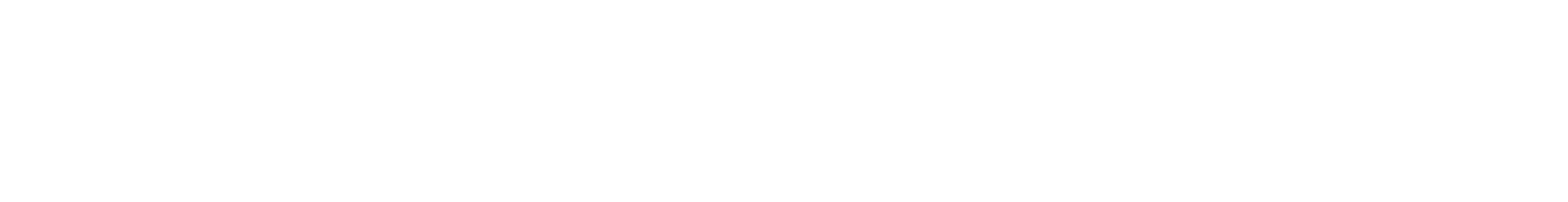遺言
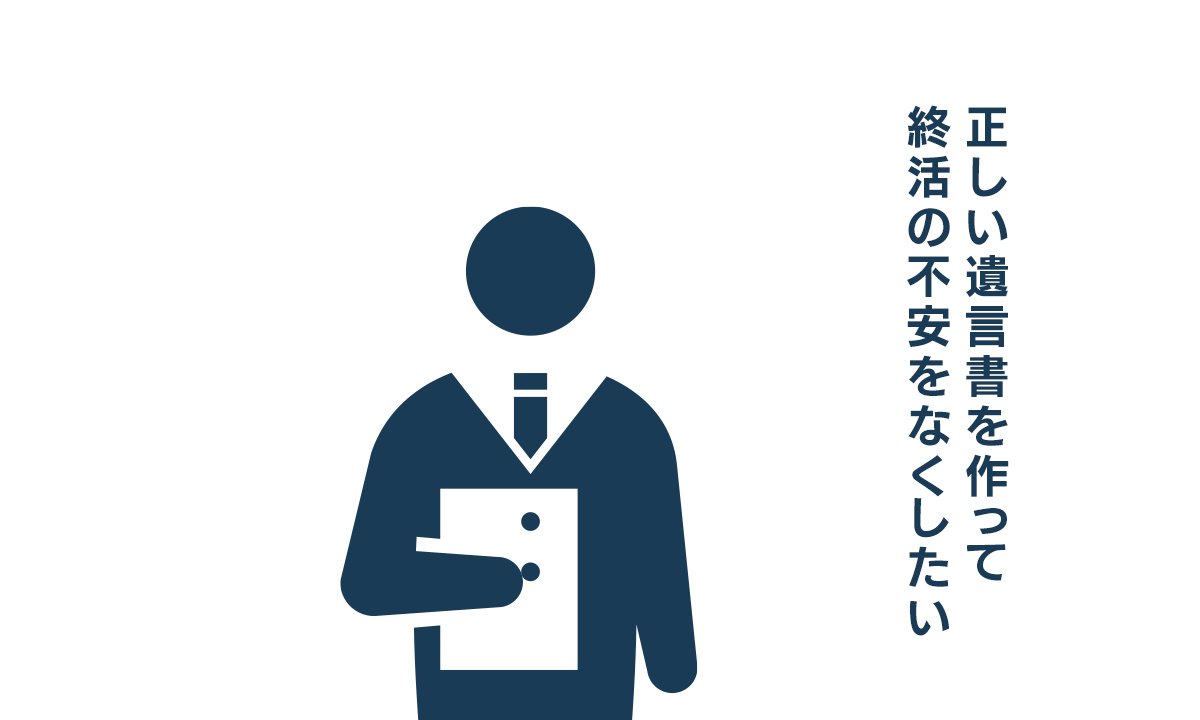
相続人が誰もいなかったとき、申立てを受けた裁判所から「相続財産清算人」が選ばれ、最終的には財産が国庫に帰属することになります。いっぽう遺言書があれば、まったく婚姻関係や血縁関係がない相手に対しても財産を残すことができます。また遺品を整理していて「遺言書」と書かれた封筒を見つけた場合、開けないようにしてください。家庭裁判所に提出する「検認」の申立てが必要になります。
遺言書を作成した方がいいときはどんなとき?
・子どもがいない夫婦
→ 配偶者だけでなく兄弟姉妹にも相続権が生じるため、遺言で配偶者に全財産を残すようにすると安心。
・内縁の配偶者がいる
→ 法律上の婚姻関係がないため、遺言がないと内縁の配偶者は相続できない。
・相続人同士の仲が悪い/もめそう
→ 遺産の分け方をあらかじめ明確にしておくことで、トラブルを防止できる。
・障がいのある子など特定の子どもや孫に多く残したい
→ 配分に差をつける正当な理由がある場合は、遺言で調整でき、法定相続分と異なる配分をしたいときは、遺言が必要。
・会社や事業を特定の後継者に引き継がせたい
→ 遺言で株式や資産を集中させ、事業承継を円滑に。
・自分の死後、寄付をしたい(社会貢献したい)
→ 遺言で「寄付」を明記しておくと確実。
・相続人がいない(もしくは疎遠)
→ 遺言がないと遺産は最終的に国庫に帰属するため、信頼できる人や団体に残したいときに必要。
・ペットの世話を頼む人に財産を残したい
→ 遺言で「世話を条件に遺贈」することで安心。
・法定相続人の一部に相続させたくない(特別な事情がある)
→ 相続人の「廃除」や「遺留分に配慮した調整」が必要で、遺言が重要になる。
・遺言をしたい人に外国籍の方や日本に帰化した方がいる中で、遺言書を書きたい。
→外国の書類を取り寄せないといけないため大変
司法書士・行政書士片山竜児事務所のしごと
自筆証書遺言の作成サポート
公正証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 書き方 | 全文・日付・署名を手書き | 公証人が本人の口述をもとに作成 |
| 費用 | 無料(ただし保管費は別) | 公証役場の手数料がかかる |
| 手軽さ | 自分一人で作れる | 公証役場に出向く必要あり |
| 安全性 | 紛失・偽造・形式不備の恐れ | 公証人が作成・原本保管で安心 |
| 検認の有無 | 家庭裁判所で検認が必要 | 検認不要(すぐに使える) |
| 保管 | 自分で保管 or 法務局保管制度 | 公証役場で保管 |
遺言作成方法
① 自筆証書遺言の作成方法(自分で書く)
ポイント:全文を自分で手書きすることが原則です。
必要な要素(すべて手書き)
- 全文(財産の分け方や相続人の名前など)
- 日付(「令和7年5月10日」など)
- 氏名
- 押印(認印でも可。実印が望ましい)
保管方法(選べる):
- 自分で保管(紛失・改ざんリスクあり)
- 法務局の「遺言書保管制度」を利用(2020年スタート、安全)
注意点:
- 書式ミスや内容不備があると無効になる恐れがあります
- 死後に使うには、家庭裁判所で「検認」が必要です
② 公正証書遺言の作成方法(公証役場で作る)
手順:
- 公証役場に事前相談(予約)
- 必要書類を準備(戸籍謄本、不動産・預金の資料など)
- 証人2人と一緒に公証役場へ行く(※証人は20歳以上)
- 本人が内容を口述し、公証人が作成
- 公証人が読み上げ、本人・証人が署名・押印
保管:
- 原本は公証役場で保管(紛失・改ざんの心配なし)
- 正本・謄本をもらって自分で管理
メリット:
- 法的に有効な遺言書が確実に作れる
- 家庭裁判所での検認が不要(すぐに相続手続きに使える)
◆ 司法書士に依頼するメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ✅ 内容の法的チェック | 無効にならないよう、必要事項や表現をきちんと整えてもらえる |
| ✅ 相続関係の調査がスムーズ | 相続人や相続財産の調査・戸籍収集なども代行してもらえる |
| ✅ 自筆遺言の添削・アドバイス | 書き方・内容・注意点など、専門的に指導してもらえる |
| ✅ 公正証書遺言の手続き代行 | 公証人との打合せや書類の準備、証人の手配も任せられる |
| ✅ 遺言執行者の指定も安心 | 死後に遺言内容を実現する「遺言執行者」に司法書士を指定することも可能 |
| ✅ 相続登記まで一括対応 | 遺言書に基づく名義変更などの手続きもそのまま頼める |
さっそく聞いてみる
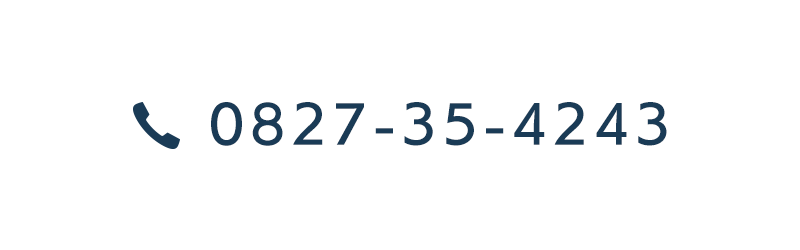
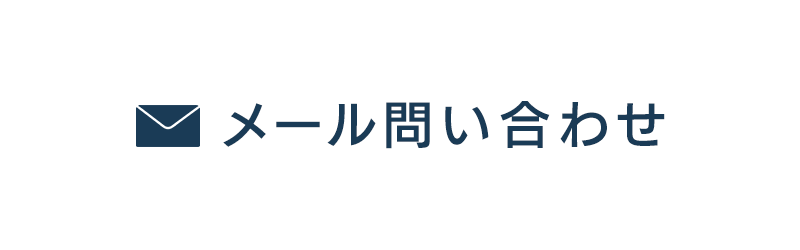
さっそく聞いてみる