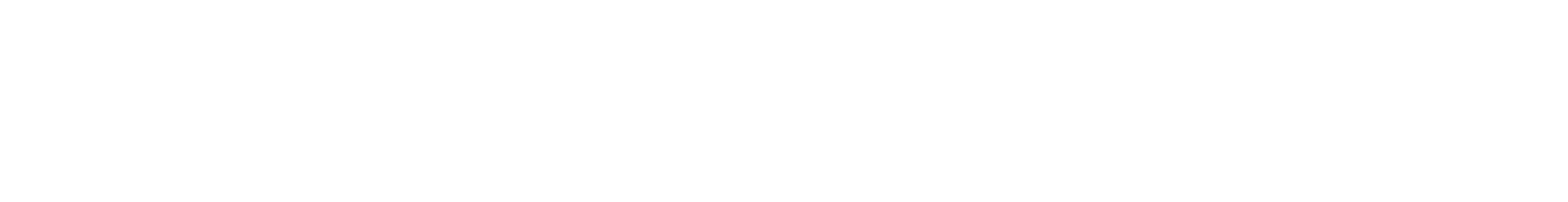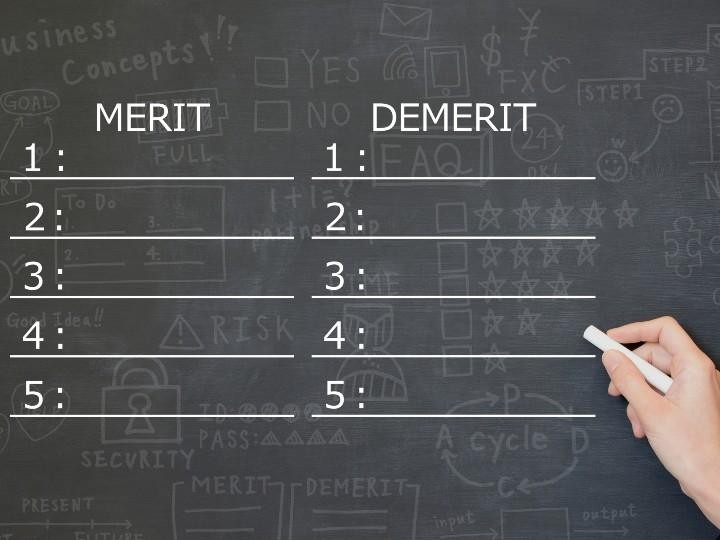
自筆証書遺言とは
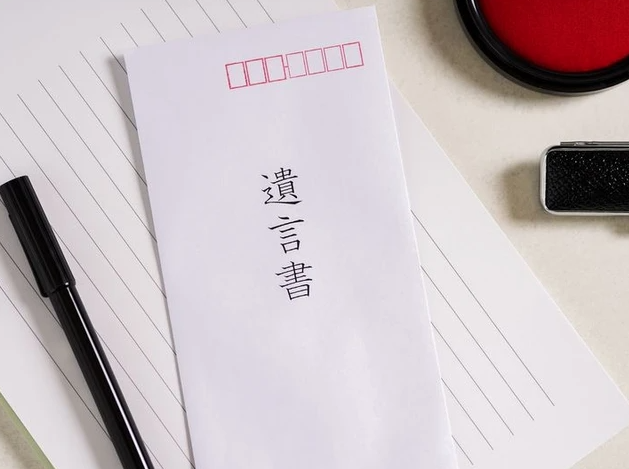
自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文・氏名・日付を自筆で書く遺言書です。
自筆証書遺言のメリット
- 自分で気軽に作成でき、書き直しもできる
紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。 - 費用がかからない
公正証書遺言の場合公証人の手数料等の費用がかかりますが、自筆証書遺言には作成費用がかかりません。 - 遺言の内容を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 要件を満たしていないと無効になる恐れ
- 紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れ
- 書き換えられたり、隠されたりする恐れ
自筆証書遺言は法務局で保管可能
自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止でき、遺言書を発見してもらいやすくなりました。法務局に支払う手数料は、1件3900円です。この制度を利用すると、通常、自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認手続きが不要となるメリットもあります。
なお、一般的に活用される遺言には、自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が本人の意向を聞きながら作成してくれるものです。費用と手間はかかりますが、書き方の誤りで無効になる恐れがなく、公証役場で預かってもらえるため紛失のリスクが少ないというメリットがあります。
岩国の法務局(岩国支局:山口地方法務局)について
場所
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
雰囲気は?
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
公証役場は使った方が良い?
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
メリット
・テキスト
・テキスト
・テキスト
デメリット
・テキスト
・テキスト
・テキスト
自筆証書遺言の要件、書き方
民法968条に「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。これらは自筆証書遺言を作成する上で、最低限守らないといけないルールと言えるでしょう。次の5点は必ず押さえておきましょう。
全文を自筆で書く(財産目録は除く)
タイトルの「遺言書」や本文など、自筆証書遺言では基本的に全ての文を遺言者が自分で書く必要があります。パソコンや代筆は認められていません。
ただし、相続財産の一覧(財産目録)についてはパソコンを使って作成したり、通帳のコピーを代用することが認められています。この場合、財産目録や通帳コピーに遺言者が自分の氏名を書き、押印する必要があります。
署名する
遺言書には必ず遺言者の署名押印が必要です。署名も必ず自筆で行いましょう。
作成した日付を明記する
遺言書の作成日を書き入れましょう。日付は正確に書く必要があり、「〇年○月吉日」などと書くと遺言書は無効です。また「〇月✕日」のように年度を書き忘れても無効になります。漏れのないように注意しましょう。
なお、複数の遺言書がある場合、新しい日付のものが有効となります。
印鑑を押す
署名したら、氏名の横に必ず押印しましょう。押し忘れた場合、遺言書は無効となります。使用する印鑑は認印でかまいませんが、実印の方が遺言者の真意に基づくことを示す観点からお勧めです。
訂正のルールを守る
遺言書の文章を訂正する場合、そのやり方も法律で厳密に定めらています。これを守らないと訂正した部分が無効となり、訂正前の遺言の効力が維持されます。訂正方法について、詳しくは「4-5. 訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す」で説明します。
自筆証書遺言の書き方のポイント
要件以外にも、押さえておくべき書き方のポイントがありますので説明します。
財産を把握するために必要な書類を集める
遺言書を作成するときには、自分にどのような遺産があるのか把握する必要があります。事前に以下のような資料を集めましょう。
・最新年度の固定資産税納税通知書
・預貯金通帳、取引明細書
・証券会社やFX会社、仮想通貨交換所における取引資料
・ゴルフ会員権の証書
・生命保険証書
・絵画や骨董品など動産の明細書
誰に、何を相続させるのか明記する
誰にどの遺産を相続させるのか、わかりやすく書きましょう。相続内容があいまいになっているとせっかく遺言書を残してもトラブルのもとになってしまう可能性があります。
たとえば「金融資産2千万円を兄弟で半分ずつ相続させ、残りの財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言を書いた場合を考えてみましょう。このような書き方をすると、たとえば現金と株の金融資産があるとき、2千万円の分け方が無数に生じるので相続人間でトラブルに発展する可能性があり、せっかく遺言書をのこした意味が無くなってしまいます。
遺言書を書くときには、紹介したひな形にあるように、長男には「○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○」、次男には「A株式会社の株式 数量○○株」などと「どの遺産を、どれだけ相続させるのか」を明記しましょう。
財産目録はパソコンで作成可能
遺言書には、どのような遺産があるのかを明らかにするための「財産目録」を作成してつけましょう。財産目録は資産内容と負債内容、合計額を示す「一覧表」です。自筆証書遺言であっても財産目録についてのみ、代筆やパソコンでの作成が可能です。また預貯金通帳の写しや不動産全部事項証明書などの資料でも代用できます。ただしパソコンでの作成や資料を代用する場合にはすべてのページに署名押印が必要です。
財産目録には各財産を正確に記載しましょう。不動産については登記簿謄本(全部事項証明書)の「表題部」で所在地番や家屋番号を、預貯金については通帳などで支店名や口座番号を確認して間違えないようにしましょう。不動産を記載するときに「住所(住居番号)」を書く方がいますが、住居番号と地番・家屋番号は違う概念ですので間違えないようにご注意ください。
遺言執行者を指定する
遺言書で遺言執行者を指定しておくと遺言内容をスムーズに実現できます。信頼できる相続人か司法書士などの専門家を指定しましょう。指定しなくても遺言書は有効ですが、その場合、家庭裁判所に遺言執行者を指定してもらう必要があります。
訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す
間違ったときや内容を書き足したいときの「加除訂正」には法律の定めるルールがあります。民法第968条では、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と定められています。
要点をまとめると、訂正・変更を行った箇所について
① その場所を示すこと
② 変更したことについて書き足すこと
③ その部分に署名をすること
④ 変更場所に印を押すこと
が必要となります。
加筆する場合
1. 加筆する箇所に吹き出しで追記します。
2. 加筆した箇所の近くの余白に、「本行で◯字加入」のように加えた文字数を記し、署名します。
3. 加筆したすぐ近くに訂正印(遺言書の署名押印に使用した印鑑と同じもの)を押印します。
訂正する場合
1. 訂正したい箇所に、元の文字が見えるよう、二重線を引きます。
※黒く塗りつぶしたり、修正液や修正テープでの修正をしてはなりません。修正前の内容が確認できないため、遺言書が無効になってしまう可能性があります。
2. 横書きの場合は二重線の上側に、縦書きの場合は二重線の横側に、正しい文言を記載します。
3. 訂正した箇所の近くの余白に、「本行で◯字削除 ◯字加入」のように記し、そのそばに署名します。
4. 二重線のすぐ近くに、元の文字が見えるよう、訂正印(遺言書の署名押印に使用した印鑑と同じもの)を押印します。
付記
付記は、訂正の場合も加筆の場合も共通です。
横書きの遺言書では最下部の余白、縦書きでは最終行の横側の余白に、付記として訂正内容の記載、遺言者氏名を署名します。
そして、「◯行目 ◯字削除 ◯字加入」のように記載し、訂正した内容すべてを列挙しましょう。
遺言書で定められる事項のうち、重要なものは以下の通りです。
● 相続分の指定
● 遺産分割方法の指定
● 相続人以外の受遺者への遺贈
● 寄付
● 一定期間の遺産分割の禁止
● 特別受益の持ち戻し計算免除
● 遺言執行者の指定
● 子どもの認知
● 相続人の廃除
● 生命保険金の受取人変更
専門家に遺言書作成をサポートしてもらうメリット
自筆証書遺言の作成のサポートを司法書士などの専門家に依頼すると以下のようなメリットがあります。
無効になるリスクを避けられる
専門家が作成した場合、要式不備で無効になるリスクはほとんどなくなります。書き方がわからない方はぜひ相談してみてください。
遺言執行者を任せられる
専門家に遺言執行者になってもらったら、死後に不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、寄付などの対応をしてくれるので遺言内容を実現しやすくなります。
遺言内容も相談できる
遺言書を書きたいけれど1人では内容を決められない方は、専門家から最適な遺言内容についてのアドバイスを受けられます。
遺留分にも配慮できる
特定の相続人に遺産の大半を分け与えた場合、他の相続人が「遺留分」を主張してトラブルになる可能性が高まります。弁護士に相談しながら作成すると、各相続人の遺留分に配慮できるので後日のトラブル防止につなげられます。
まとめ 司法書士など専門家への相談も検討を
手軽に書ける自筆証書遺言ですが、自己判断で作成すると、無効になったり、トラブルにつながったりするリスクがあります。弁護士ら相続の専門家に相談しながら確実に内容を実現できる遺言書を作成しましょう。