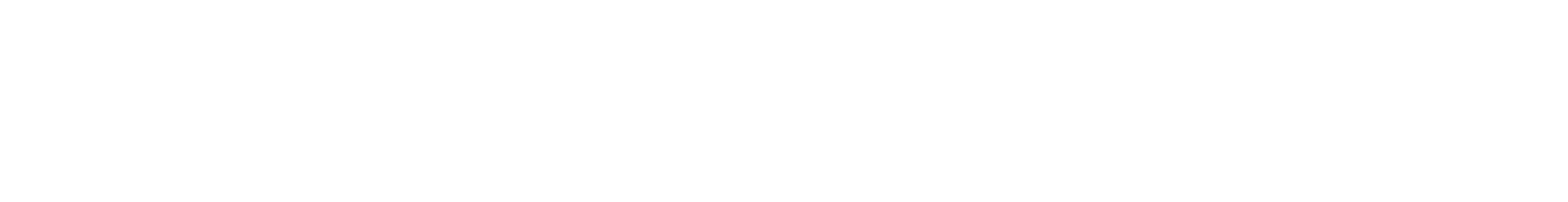亡くなった人が遺言書を残していれば、遺言書に従って相続手続きが行われます。
ただし、相続手続きを行う前に、遺言書の検認申立が必要になるケースがありますから注意しておきましょう。
ここでは、遺言書の検認申立について説明します。検認申立の必要書類や手続きの流れを知っておきましょう。
遺言書の検認とは
検認とは、遺言書の内容を明確にすると同時に、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせる手続きです。検認には、遺言の偽造や変造を防止するという意味もあります。
検認手続きは、家庭裁判所で行われます。
なお、検認は、遺言書を保全する手続きで、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。遺言の無効を確認したい場合には、別途遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を起こす必要があります。
自筆証書遺言は検認が必要
検認が必要なのは、公正証書遺言以外の遺言になります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
遺言書のうち一般に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
自分で手書きして作る遺言書が自筆証書遺言で、公証人に頼んで公正証書にしてもらう遺言書が公正証書遺言になります。
故人が手書きした遺言書が出てきた場合には、検認が必要になりますので覚えておきましょう。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されており、偽造や変造のおそれがないので、検認は不要です。
遺言書の保管者や発見者には検認申立をする義務がある
手書きの遺言書が残されていた場合には、必ず検認を申し立てなければなりません。遺言書の保管者や発見者は、民法上、検認申立が義務付けられています。
検認申立には明確な期限は設けられていませんが、「遅滞なく」申し立てなければならないとされています。
遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言を保管しているケースが多いと思います。遺言を保管している遺言執行者は、相続開始後、速やかに検認申立をしましょう。
検認手続きを経ないまま遺言を執行場合には、5万円以下の過料(罰金)に処せられる旨も規定されています。
たとえ相続人全員が検認なしで合意していても、検認を省略できるわけではありません。
遺言書は検認が終わるまで開封しないこと
遺言書は、そのままの状態で検認を受ける必要があります。遺言の開封は検認手続きの際に行いますから、封がしてある遺言は勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所以外で遺言の開封を行った場合には、5万円以下の過料に処せられます。
なお、うっかり遺言書を開封してしまった場合でも、遺言が無効になるわけではありません。開封してしまった遺言書も、速やかに検認を受けましょう。
相続法改正により遺言書の保管制度を利用すれば検認が不要に
平成30年に相続法(民法の相続について規定した部分)が改正され、相続のルールが変わりました。これに伴い、遺言書保管法という法律も制定され、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度が創設されました。
遺言書保管法は、令和2年7月10日に施行される予定です。
遺言書の保管制度を利用して法務局に保管されている自筆証書遺言については、民法の遺言書の検認の規定は適用されず、検認不要となります。
遺言書の検認申立の申立先と必要書類
遺言書の検認申立は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
検認申立の必要書類は、次のとおりです。
①検認申立書(家事審判申立書)
②戸籍謄本
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、その他相続関係がわかる戸籍謄本一式が必要になります。
遺言書の検認申立にかかる費用
遺言書の検認申立をするときには、遺言書1通につき800円の手数料がかかります。手数料は、収入印紙を購入し、検認申立書に貼付して納めます。
検認申立時には、裁判所からの連絡に使う郵便切手も提出しなければなりません。切手の金額は裁判所によって異なりますので、提出する家庭裁判所に確認しましょう。
遺言書の検認申立を弁護士などの専門家に依頼した場合には、別途専門家の報酬がかかります。専門家の報酬については、依頼する事務所によって異なります。
遺言書の検認手続きの流れ
遺言書の検認手続きの流れは、次のようになります。
検認申立の際には、相続関係がわかる戸籍謄本一式が必要です。戸籍謄本収集には時間がかかることがありますので、早めに取りかかりましょう。
検認申立書も作成します。検認申立書には相続人全員の住所を記入する必要があるので、住所がわからない相続人は住所を調べましょう。
戸籍謄本が揃ったら、申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。収入印紙や郵便切手も忘れないようにしましょう。
検認の申立があったら、家庭裁判所は検認期日を決め、相続人全員に通知します。なお、申立人以外の相続人は、検認期日に必ず出席しなくてもかまいません。相続人の中に病気や高齢で裁判所に行けない人がいても問題ないということです。
検認期日には、相続人の立ち会いのもと、遺言書が開封されます。申立人には、遺言書がどこにあったかなどの質問がされることもありますので、質問に答えます。
検認が終わると、遺言書に検認済証明書を付けてもらえます。検認済証明書の発行には申請が必要なので、家庭裁判所に申請します。
検認済証明書が付いていないと、役所や金融機関に遺言書を提出して手続きしようにも、受け付けてもらえません。検認済証明書の申請には150円の手数料がかかります。
遺言書の検認手続きにかかる時間
遺言書の検認申立をするには、戸籍謄本を揃えなければなりません。相続関係が複雑な場合などには、取得しなければならない戸籍謄本の数が多くなり、申立までに時間がかかってしまいます。また、検認申立後、検認期日が入るまで1~2か月程度はかかります。その間は、相続手続きを進められません。
相続放棄を検討しなければならない場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所での申述手続きが必要です。遺言書の内容を確認しなければ、相続放棄するかどうか決められない場合には、期間延長の手続きをしておきましょう。
遺言書の検認が終わった後の相続手続き
遺言書ですべての財産について承継先が指定されていれば、遺産分割協議は不要です。
遺言書の検認が終わったら、検認済証明書の付いた遺言書を提示して、相続手続き(名義変更)を行います。
不動産の相続手続きをするときには、遺言書を添付して法務局で相続登記を行います。
また、預貯金の相続手続きを行うには、遺言書を金融機関に提出し、払い戻しを受けることになります。
まとめ
亡くなった人が自筆証書遺言を残している場合には、相続手続きをする前に、遺言書の検認申立をする必要があります。自筆証書遺言は、検認済証明書が付いていなければ、相続手続きには使えないことを知っておきましょう。
遺言書の検認手続きには時間がかかります。
遺言書で相続対策を行うなら、検認不要の公正証書遺言にするのがおすすめです。