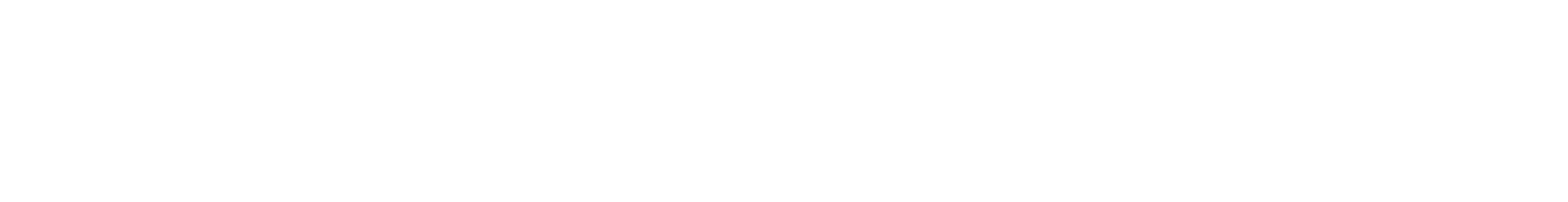手続き解説– tag –
-

遺産分割調停申立て
【遺産分割調停とは】 遺産分割調停とは、遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合に利用することができる、家庭裁判所の手続きです。 家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、話し合いによって相続人全員による... -

生前贈与
相続は被相続人が亡くなることで発生しますが、生前贈与とは存命中に贈与することをいいます。また、生前贈与では、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能です。例えば、孫に財産を残したい場合は、遺言書に孫への相続について記載する以外にも、生... -

遺言書検認申立て
亡くなった人が遺言書を残していれば、遺言書に従って相続手続きが行われます。ただし、相続手続きを行う前に、遺言書の検認申立が必要になるケースがありますから注意しておきましょう。 ここでは、遺言書の検認申立について説明します。検認申立の必要書... -

不在者財産管理人選任申立て
不在者財産管理人とは、行方が分からず連絡がまったくとれない行方不明者(不在者)の財産を管理する人です。相続の場面では、行方不明の相続人に代わり財産を管理する人をさします。 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人の1... -

渉外登記
渉外登記とは、不動産取引や相続に関する登記手続きにおいて外国籍の方の関与や、外国で発行された文書が必要となるなど、国際的な要素を含む登記手続きのことを指します。具体的には、外国人が日本の不動産を取得・処分した場合や、被相続人や相続人が外... -

法定相続情報一覧図の取得
法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。簡単に言うと「相続関係が一目でわかる公的証明書」であり、法務局の登記官により証明されます。 この一覧図は平成29年5月から運用を開始した「法定相続情報証明制度」... -

相続財産清算人選任申立て
相続財産清算人とは、相続人が存在しない故人の相続財産の清算を行う人のことで、その相続財産に関わる利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることができます。 【相続財産清算人が必要とされるケース】 相続財産清算人が必要とされるケースの代表例は... -

相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。近年、相続した土地を手放したいというニーズが高まっています。なぜなら、土... -

限定承認申述書
限定承認とは、あなたが故人の借金を相続したとしても、相続した遺産の範囲内で借金を返済すればよいという制度です。不動産などの相続したい遺産がある一方、どれくがらい借金があるか全く分からないといったケースの場合、この制度が役に立ちます。 【「... -

相続放棄申述書
相続放棄申述書とは、相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうための提出書類です。この申述書を家庭裁判所に提出することで、相続放棄の審査が始まります。相続放棄申述書には決まった書式があり、裁判所のホームページなどから入手ができます。 【相続放棄申...
12