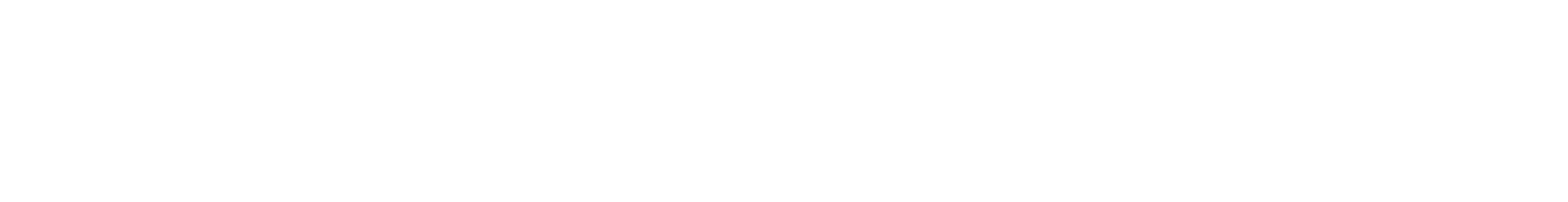相続財産清算人とは、相続人が存在しない故人の相続財産の清算を行う人のことで、その相続財産に関わる利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
相続財産清算人が必要とされるケース
相続財産清算人が必要とされるケースの代表例は、相続人がいない人の相続財産を受け取ろうとする場合です。具体的には、次の【A】のようなときに【B】のような行為をする場合が考えられます。
【A】
・相続人全員が相続放棄した。
・もともと相続人がいない(父母、祖父母が全員亡くなり、兄弟姉妹、配偶者、子がいない場合など)。
【B】
・被相続人に対する債権を債権者が回収しようとする場合
・被相続人の特別縁故者が、相続財産の分与を受けようとする場合
・被相続人が共有していた不動産の共有者が、被相続人の持分を取得しようとする場合
・その被相続人が別の相続の遺産分割協議をすべき相続人の一人である場合
上記【A】の例のように故人に相続人がいない場合、相続財産は債権者や受遺者に対して清算を終えた後は国庫に帰属します。ただし、故人と生計を同じくしていた者、故人の療養看護に努めた者、その他故人と特別な縁故があったと認められた者は、家庭裁判所が認めた範囲で財産を取得することができます。
なお、相続財産清算人は、以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、民法の改正により令和5年4月1日から名称が変更されました。
相続財産清算人の仕事
相続財産清算人は、一般的には亡くなった人の居住地域で活動している司法書士・弁護士が選ばれることがほとんどで、次のような業務を行います。
■相続財産の調査・遺産目録の作成
■相続財産の管理・処分
■相続債務の支払
相続財産清算人の選任手続きの流れ
選任手続きは、次のような流れで進めます。
1.必要書類の準備
2.家庭裁判所への申立て
3.選任審判
相続財産清算人の選任申し立てに必要な書類
選任申し立てに必要な書類は次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・被相続人の住民票除票または戸籍附票(本籍の記載付き)
【被相続人の子(およびその代襲者)の中に死亡している人がいる場合】
・その者の出生から死亡までの戸籍謄本一式
【被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲者)の中に死亡している人がいる場合】
・その者の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・相続財産を証明する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金通帳の写し、残高証明書など)
・申立人と被相続人との利害関係を証明する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書写しなど)
【相続財産清算人の候補者がいる場合】
・候補者の住民票または戸籍附票
相続財産清算人を選任するための費用と報酬について
相続財産清算人の選任申し立ての費用
相続財産清算人の選任申し立てに必要な費用は次のとおりです。
- 収入印紙800円分
- 予納郵便切手
- 官報公告料
相続財産清算人の報酬
相続財産清算人の報酬は、相続財産清算人が清算業務を終えるときに、報告書とともに報酬付与申立てを行い、業務量や財産規模等を踏まえ、家庭裁判所が報酬額を決定します。
この報酬は相続財産から支払われます。
もし相続財産が清算業務を行うのに十分でない場合、選任申立ての段階で「予納金」を納めなければならないことがあります。
選任の請求にあたり「予納金」を納める必要
相続財産のうち預貯金や換価性のある財産が少ない場合、相続財産清算人への報酬や清算事務にかかる費用に充てるため、「予納金」を家庭裁判所に納めなければならない場合があります。ケースによりますが、予納金は大体50万円から100万円程度です。ただし、老朽化した家屋を解体しなければならない場合など、多額の費用の支出が見込まれる場合、予納金額がより高額になることがあります。
相続財産清算人の報酬や清算事務にかかる費用が相続財産から支払えれば、予納金は申立人に返還されます。
相続財産清算人の選任後の流れ
家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されると、次のような手順で相続財産の管理・処分が行われます。法律でさまざまな手続きが定められており、すべての手続きが終わるまでに通常1年程度かかります。
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所によって相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告が行われます。
この公告は6か月以上の期間を定めて行われ、公告の期間内に相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
一方、この公告によって相続人が現れた場合には、相続財産は相続人に与えられ、手続きは終了します。
以前は、相続人の捜索の公告は、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の後に行われていました。
民法の改正により、令和5年4月1日以降に相続財産清算人が選任された場合は、選任の公告とまとめて同時に行うことになりました。
相続財産清算人は相続債権者・受遺者に対して請求の申し出をするように公告しなければなりません。
相続債権者・受遺者の存在がわかっている場合には、相続財産清算人はこの公告とは別に個別に請求を申し出るよう促します。
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間は2か月以上必要ですが、上記の選任・相続人の捜索の公告の期間内に終了するようにしなければなりません。
相続債権者・受遺者は、この期間内に申し出をしなければ遺産を受け取ることはできません。
以前は、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告は、選任の公告が終了したのち、相続人の捜索の公告の前に行われていました。
民法の改正により、令和5年4月1日以降に相続財産清算人が選任された場合は、選任・相続人の捜索の公告の期間内に並行して行うことになりました。
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間が終了すれば、相続財産清算人は、相続財産から相続債権者・受遺者に対して支払いを行います。
財産分与を受けたい特別縁故者がいる場合、その者は、相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告の期間満了後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者への財産分与を申し立てる必要があります。
相続人も特別縁故者もいない場合であって、被相続人の相続財産に不動産の共有持分がある場合には、その不動産の共有持分は他の共有者に分け与えられます。
以上の手続きを経てもなお残る相続財産があれば、最終的に国庫に帰属、すなわち国のものとなります。