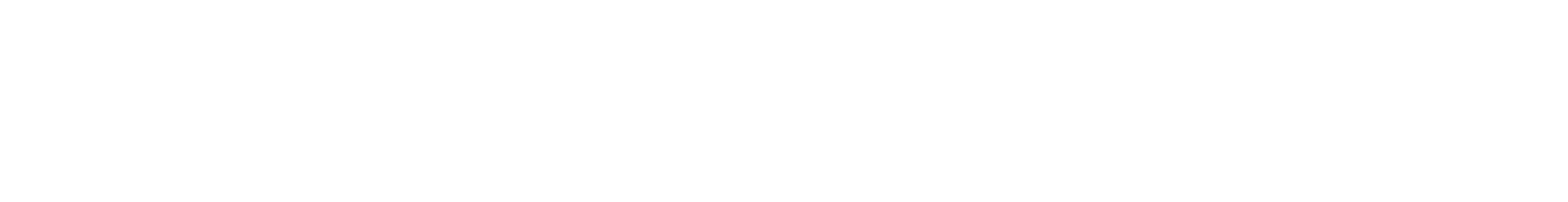1. はじめに
事業承継の重要性
企業が永続的に発展するためには、事業承継は避けて通れません。
事業承継は単なる経営権の移行ではなく、企業の持つ知識、経営の秘訣、理念など多岐にわたる要素を次世代に引き継ぐことを意味します。
この記事では、事業承継の基本的な流れや方法、成功するためのポイントについて詳しく解説します。
事業承継で引き継がれるもの
事業承継では、有形資産と無形資産の両方が引き継がれます。
有形資産
株式、設備、建物、資金など、企業運営に欠かせない物理的な資産。
無形資産
技術、ノウハウ、顧客情報、人脈、企業理念、ブランドなど、企業の競争力を支える知的資産。
法人向け事業継承の現状と課題
日本の事業承継の現状
日本では少子高齢化の進行に伴い、多くの中小企業が後継者不足に悩んでいます。 日本政策金融公庫の調査によれば、後継者が決まっている中小企業は全体の約12%に過ぎません。 多くの企業が事業継承を行わずに廃業を選択しています。
事業承継の課題
1.後継者の選定と育成
適切な後継者を見つけ、経営者としての教育を施すことが重要です。
2.税金対策
事業承継時には、相続税や贈与税の負担が発生します。
3.資金調達
従業員承継や第三者承継では、後継者が経営権を得るための資金調達が必要です。
公的支援や融資制度を活用しましょう。
4.情報管理とコミュニケーション
事業承継は、従業員や取引先などの関係者への情報共有が欠かせません。
2.事業継承の基本知識
事業継承とは何か
事業継承の定義と重要性
事業継承とは、企業の現経営者がその経営権を次の経営者に引き継ぐことを指します。 具体的には、経営権、経営理念、企業の資産、負債など、企業に関連するすべてのものを引き継ぐことを意味します。
事業継承の種類(親族内継承、従業員継承、第三者継承)
親族内継承
親族内継承は、現経営者の配偶者や子どもなど、親族に事業を引き継ぐ方法です。
家族の絆や信頼関係が基盤となり、従業員や取引先からの信頼を得やすいのが特徴です。
後継者選定が容易で、早期教育が可能なため、経営理念や価値観の継承がスムーズに行えるメリットがあります。
税金面の注意が必要です。親族内で事業を引き継ぐ際には、相続税や贈与税が発生します。
従業員継承
従業員継承は、現経営者の親族ではなく、会社の従業員に事業を引き継ぐ方法です。
主に役員や幹部社員が後継者となるケースが多いです。
従業員継承のメリットは、後継者が既に会社の業務や経営方針を理解している点です。
従業員が後継者となるためには、教育や訓練には時間と費用がかかります。
また、従業員が会社の株式を購入する際には、資金が必要となります。
中小企業では公的な支援や融資を活用しましょう。
第三者継承
第三者継承は、現経営者の親族や従業員以外の外部人材に事業を引き継ぐ方法で、一般的にはM&A(合併・買収)を通じて行われます。
最大のメリットは経営資源の最適化と事業の継続性確保で、買い手が経営経験や資金力を持つことで企業の成長が期待され、現経営者は売却益を得られます。
しかし、外部人材が会社の文化や理念に適応するには時間がかかるため、適切な買い手を見つけるための仲介者やコンサルタントの選定が重要です。
事業承継における法律用語の解説
事業承継の法律用語
1.経営権
経営権とは、企業の経営に関する重要な意思決定を行う権利です。
株式会社の場合、経営権は通常、議決権付き株式の過半数を所有することで確立されます。
経営権の移譲には、株式の譲渡や贈与、相続などの方法があります。
2.株式譲渡
株式譲渡とは、企業の株主が自ら保有する株式を他者に売却することを指します。 株式譲渡は、事業承継の一環として後継者に経営権を移す手段として広く利用されます。株式の譲渡には法的な手続きが必要であり、譲渡契約の締結や株主名簿の変更などが行われます。
3.相続税・贈与税
事業承継の際には、相続税や贈与税が課税されることがあります。 相続税は、経営者が亡くなった際に遺産として引き継がれる資産に対して課される税金です。 一方、贈与税は、生前に経営者が後継者に資産を譲渡する場合に課されます。
4.贈与
贈与とは、無償で他者に財産を譲り渡す行為を指します。 事業承継においては、経営者が後継者に対して株式や資産を贈与することで、スムーズな承継を実現することができます。贈与は、税金対策になります。
5.M&A(Mergers and Acquisitions)
M&Aは、企業の合併や買収を意味します。事業承継の一手段として、経営者が自社を他の企業に売却することで事業を継続させる方法です。
M&Aには、企業価値の評価や契約の交渉、法的手続きなどが含まれます。
3. 事業継承の準備と計画
事業継承のタイミングと準備の重要性
事業承継を始める適切なタイミング
経営者がリタイアを考え始めた時点で、すぐに事業承継の準備を始めることが理想です。
一般的には、少なくとも5年以上前から準備を開始することをおすすめします。
事業承継の準備で考慮すべきポイント
1.後継者の選定と育成
2.事業承継計画の策定
3.税務対策
4.従業員や取引先への周知
事業承継計画の立て方
1.自社の経営状況の分析
まずは、現状の経営状況を正確に把握することが重要です。 財務状況、業績の推移、経営資源(人材、物的資源、資金、技術、ノウハウ、情報、時間)などを詳細に分析し、強みと弱みを明確にします。
2.後継者の選定と育成
親族内から選ぶ場合、従業員から選ぶ場合、または外部から迎える場合のいずれも、それぞれのメリットとデメリットを考慮します。選定後は、後継者の育成計画を立て、経営スキルや企業理念の継承を確実に行います。
3.事業承継の方法と手続き
事業承継には、親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)の三つの主要な方法があります。
企業の状況に応じて最適な方法を選択します。
4.事業承継計画の策定
具体的な事業承継計画を策定します。
計画には、承継のスケジュール、後継者の育成プログラム、関係者への説明と同意の取得などが含まれます。
また、計画の進捗を定期的にチェックし、必要に応じて修正を加えましょう。
5.コミュニケーションと信頼関係の構築
後継者との信頼関係を築くために、透明なコミュニケーションが重要です。
6.法務・税務対策の準備
相続税や贈与税の負担軽減策として、事業承継税制の活用が効果的です。
専門家の助言を受けながら、効果的な対策を取りましょう。
7.事業承継後のフォローアップ
事業承継が完了した後も、フォローアップを継続します。
後継者が新たな経営体制に順応し、企業の持続的な発展を実現できるように支援することが重要です。
現経営者が顧問として後継者をサポートする体制を整えることも有効です。
継承先の選定方法
後継者候補が現経営者の親族、社内の従業員、外部の第三者の場合もあります。
後継者を選定した後は、彼らの経営スキルを育成していきます。
経営知識や実務経験を積ませることで、スムーズな事業承継となります。
4. 事業継承の具体的手順
事業承継の基本的な流れ
事業承継の準備ステップ
1.自社の現状把握
- 財務状況:最新の財務諸表を確認し、資産、負債、純資産の状況を把握します。
- 経営状況:売上や利益の動向、顧客数や市場シェアなどの経営指標を分析します。
- 事業資産:不動産、設備、知的財産などの有形・無形資産のリストを作成します。
これらの情報を基に、自社の強みや弱み、機会や脅威(SWOT分析)を明確にし、事業承継に向けた戦略を立てるための基礎資料とします。
2.後継者の選定
次に、後継者を選定します。 後継者は親族内、社内の従業員、または外部の第三者から選ぶことが一般的です。
- 経営能力:経営者としてのスキルや経験、リーダーシップの有無を評価します。
- 意欲:後継者候補の意欲や覚悟を確認し、事業を引き継ぐ意思があるかを確かめます。
- 人間関係:従業員や取引先との信頼関係を築ける人物かどうかも重要なポイントです。
3.事業承継計画の策定
事業承継計画は、後継者に事業を円滑に引き継ぐための具体的な計画書です。
- 引き継ぎスケジュール:事業承継のタイミングや手順を明確にします。
- 役割分担:現経営者と後継者の役割や責任を具体的に決めます。
- 教育計画:後継者に対する教育内容や期間を設定します。
- リスク管理:事業承継に伴うリスクを洗い出し、それに対する対策を立てます。
4.事業承継の実行
計画が整ったら、実際に事業承継を進めていきます。
- 資産の移転:株式や不動産などの資産を後継者に移転します。
- 組織変更:必要に応じて、取締役会や株主総会を開催し、役員の選任や定款を変更します。
- 社内外への通知:事業承継が完了したら、従業員や取引先に通知し、新体制のスタートを正式に告知します。
5.事業承継後のフォローアップ
新しい経営体制が安定するまでの間、フォローアップが必要です。
- 経営状況のモニタリング:定期的に経営状況をチェックし、必要に応じてサポートします。
- 従業員のケア:従業員の不安や疑問に対応し、モチベーションを維持するためのコミュニケーションを重視します。
- 経営改善:新たな経営者が自分のスタイルを確立し、事業を発展させるための改善活動をサポートします。
事業継承の必要な書類と手続き
必要な書類
1.株式譲渡契約書
株式譲渡契約書は、事業承継において経営権を移転するために必要な書類です。
経営権を持つ株式を譲渡する際には、売り手と買い手が合意した条件を明記し、双方が署名・捺印します。
2.株主名簿
株主名簿は、会社の株主の情報を一覧にしたもので、事業承継時に経営権の移転を確認するために必要です。
株式の譲渡が行われた後には、名簿を更新し、新しい株主の情報を正確に反映させます。
3.会社定款
会社定款は、会社の基本的な運営方針や規則を定めた書類です。
事業承継に伴い、定款の変更が必要となる場合があります。
例えば、代表取締役の変更や事業目的の追加などがあります。
4.納税証明書
事業承継に伴う税務手続きのためには、納税証明書が必要です。
売り手および買い手の税務状況を確認し、適切な税務処理を行います。
5.遺言書(親族内承継の場合)
親族内での事業承継を行う場合には、現経営者が遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書によって、後継者に対する事業承継の意志を明確にし、法的なトラブルを未然に防ぎます。
必要な手続き
1.承継計画の策定
まずは、事業承継のための計画を策定します。
計画には、後継者の選定、承継のタイミング、必要な手続きなどを具体的に記載します。
2.後継者の教育・訓練
後継者が事業を円滑に引き継げるよう、必要な教育や訓練を行います。
経営に関する知識やスキルだけでなく、会社の理念や文化も引き継ぐことが求められます。
3.株主総会の開催
株式譲渡や役員の変更など、重要な決定事項は株主総会で承認を得る必要があります。
株主総会を適切に開催し、必要な議題を議決することで、法的な手続きを進めることができます。
4.登記手続き
代表取締役の変更や定款の変更など、法的な変更事項は法務局に登記を行います。
登記手続きが完了することで、法的に事業承継が成立します。
5.税務申告
事業承継に伴う税務手続きを適切に行います。
株式譲渡に関する譲渡所得税や相続税・贈与税の申告が必要です。
税理士などの専門家に依頼し、適切な税務処理を行いましょう。
事業継承の税務対策(相続税、贈与税、事業承継税制)
相続税と贈与税
事業承継において、相続税と贈与税は大きな負担となることがあります。
相続税
相続税は、被相続人が死亡したときに、その財産を相続した人に課される税金です。
事業承継においては、企業の資産価値が高額のため、高額な相続税が発生します。
相続税の課税対象には、土地、建物、株式などの資産が含まれます。
相続税の計算には基礎控除が適用されますが、それを超える部分に対しては累進税率が適用されます。
相続税の負担を軽減するためには、遺産分割の計画や生前贈与の活用が効果的です。
贈与税
贈与税は、財産を無償で譲渡する際に課される税金です。
事業承継の一環として、自社株式や資産を後継者に贈与する場合、この贈与税が問題となります。
贈与税の税率も累進課税となっており、高額な贈与には高い税率が適用されます。
贈与税の負担を抑えるためには、暦年課税と相続時精算課税の二つの制度を理解し、効果的に利用することが重要です。
事業承継税制
事業承継税制は、事業承継を円滑に進めるための税制優遇措置です。
これにより、多額の相続税や贈与税による企業経営の圧迫を防ぎます。
納税猶予制度
事業承継税制の中心的な機能は、相続税や贈与税の納税猶予制度です。
一定の要件を満たすことで、相続税や贈与税の納税を猶予されることがあります。
具体的には、後継者が事業を引き継いでからも一定期間継続して経営を行うこと、雇用の維持などが要件となります。
5. 成功する事業継承のポイント
後継者の育成と教育
事業承継の重要性
日本の企業の多くが少子高齢化に直面しており、後継者不足が深刻な問題となっています。
日本政策金融公庫の調査によれば、国内の中小企業で後継者が決まっているのはわずか12%程度であり、後継者がいないために廃業を余儀なくされる企業も少なくありません 。
後継者育成のための具体的なステップ
1.早期の後継者選定
後継者の育成には長い時間がかかります。
そのため、可能な限り早期に後継者を選定し、育成を開始することが重要です。
親族内での継承が難しい場合は、従業員や外部の第三者を後継者候補として検討することも一つの方法です 。
2.実務経験を積ませる
後継者に対しては、経営に必要な実務経験を積ませることが不可欠です。
例えば、現場の業務を理解させるために様々な部門を経験させたり、経営会議に参加させたりすることで、実際の経営の流れや意思決定のプロセスを学ばせることができます。
3.経営スキルの教育
後継者には経営に必要なスキルを習得させることも重要です。
ビジネススクールや専門の研修プログラムを活用し、財務管理やマーケティングなどのスキルを体系的に学ばせることが有効です。
教育の効果を最大化するために
1.信頼関係の構築
定期的にコミュニケーションを取り、後継者の意見や考えを尊重し、適切なフィードバックを与えることで、信頼関係を強化することができます。
2.長期的な視点を持つ
後継者の育成は長期的な視点を持ち、計画的に教育プログラムを設計します。
また、育成プロセスにおいては、柔軟に計画を見直し、必要に応じて調整しましょう。
継承後の支援体制の構築
継承後の経営者をサポートする体制を構築することが非常に重要です。
経営アドバイスとして、コンサルタントやメンターによる定期的な支援を行い、技術サポートには専門家の知識を提供します。
従業員の教育とサポート体制も整えます。
継続的な教育プログラム、メンタリング制度、コミュニケーションの強化が必要です。
財務および法務のサポートも欠かせません。
財務専門家のアドバイスや法務専門家によるサポートで、契約や法的問題に対処します。
事業承継後のモニタリングとフィードバックも継続的に行います。
定期的なレビューと従業員のパフォーマンス評価で、経営状況を把握し、改善点を見つけます。
課題解決のためのリソース提供も重要です。技術的なリソースや人材リソースを確保し、企業の競争力と成長を支援します。
事業継承における信頼関係の構築
親族内継承における信頼の重要性
親族内継承は、日本の中小企業で一般的な方法です。
家族内での継承は、親密な関係が基盤となるため、従業員や取引先からの信頼を得やすいという利点があります。
従業員との信頼構築
従業員の信頼を得るためには、透明性とコミュニケーションが重要です。新しい経営者が従業員の声に耳を傾け、企業のビジョンや価値観を共有することで、従業員の支持と協力を得ることができます。
取引先との信頼関係の維持
新しい経営者が取引先に対して誠実で一貫した対応を続けることで、信頼を失わずに済みます。
信頼関係の継承
現経営者が築き上げた信頼を次の世代に引き継ぐためには、長期的な視点での計画が必要です。
新しい経営者が現経営者の価値観や経営理念を理解し、それを実践することで、信頼関係を自然に継承することができます。
課題と対策
事業承継には、後継者の教育や税金対策など、多くの課題が伴います。
また、第三者の専門家を活用することで、より客観的なアドバイスを受けることができます。
6. 事業継承の成功事例
成功事例1: 親族内継承による成功
ある地方の老舗旅館では、長年にわたり家族経営を続けていました。
創業者である祖父から父へ、そして現経営者である息子へと三代にわたり経営が引き継がれています。
成功の要因は、家族間の強い絆と信頼関係にあります。
経営を引き継ぐ際、父は息子に対して厳しい経営訓練を施し、現場での実務経験を積ませました。
また、従業員や地元住民との関係も大切にしました。
息子が経営を引き継いだ後も、地域の観光業界においても高い評価を受けています。
成功事例2: 従業員継承による成功
ある中小企業では、長年勤めていた取締役が後継者として選ばれました。
この取締役は元々現場の第一線で働き、会社の成長に大きく貢献してきた人物でした。
後継者選定にあたって、現経営者は彼の業務能力や人間性も評価しました。
新しい経営者として選ばれた取締役は、まず現経営者から経営知識や財務管理の指導を受けました。
また、従業員とのコミュニケーションを重視し、経営者としての信頼を築く努力を続けました。
成功事例3: 第三者継承による成功
ある製造業の会社を取り上げます。
この会社は、長年にわたり高品質な部品を製造しており、独自の技術と信頼できる顧客基盤を持っていました。
しかし、経営者が高齢化し、後継者が見つからないため、第三者継承を選択しました。
この会社はM&A仲介会社を通じて、業界経験が豊富な第三者に事業を譲渡しました。
買い手は事前に会社の業務内容や市場での評価を詳細に調査し、その結果、この会社の技術力と顧客基盤を非常に評価しました。
譲渡後も、元経営者が一定期間アドバイザーとして関わり、スムーズな引き継ぎを実現しました。
7.まとめ
事業承継は企業の未来を決定づけるために欠かせません。
後継者の選定と育成には時間がかかり、また税務対策や法律手続きも複雑であるため、専門家の助言を得ることが重要です。
事業承継が成功すれば、企業の存続と発展が確保されるだけでなく、従業員や取引先、地域経済にも大きな利益となります。
早期に計画を立て、後継者との信頼関係を築き、適切なサポート体制を整えることで、事業承継を円滑に進めましょう。
企業の未来を見据えた確かな事業承継を実現するために、計画的かつ丁寧な準備を進めていきましょう。