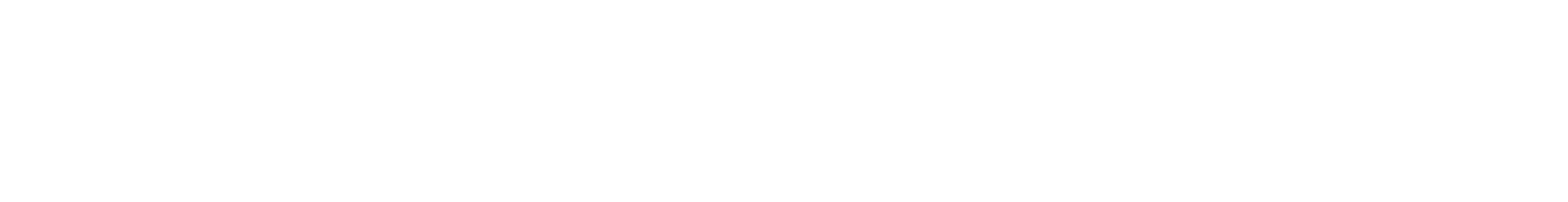片山様指定記事▼
参考にした記事▼

相続は誰にでも訪れる可能性があり、その際には多くの手続きと法律的な知識や対応が求められます。
この記事では、相続の基本から注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。
相続がどのように始まるのか、どのような財産が相続の対象となるのか、そして相続人は誰であるのか。
また、相続における遺産分割のルールなど、トラブルになりやすい事を知っておきましょう。
相続が発生するタイミング
相続は、被相続人の死亡によって自動的に発生し、法律上の定義により、亡くなった人が保有していた財産や権利、義務をその法定相続人が引き継ぐことになります。
相続が開始されるのは死亡の事実が確定した時点です。
自然死のほか、法的な死亡宣告ではその時点を、事故や災害で行方不明になった場合は、法的に死亡が宣告された時や、行方不明になってから一定期間が経過した後の失踪宣告も、相続の開始を意味します。
相続は、財産の承継だけでなく、負債やその他の義務の承継も含むため、相続が発生するタイミングを正確に理解し、適切に対処することが重要です。相続の発生後は、遺産分割協議を始めとする一連の手続きが続くため、相続人は亡くなった人の死を知った時点で速やかに行動を開始する必要があります。
誰が相続人になるの?
相続人を決定する際、遺言書の有無が大きな影響を及ぼします。
被相続人が遺言を残していた場合、遺言に記載された指示に従って遺産が分配されます。
遺言書で指定された相続人のことを「指定相続人」と呼びます。
これに対して、遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産については、「法定相続人」が遺産を受け継ぎます。
また、ある法定相続人が亡くなっている場合、その人の相続分をその子供や孫が引き継ぐ「代襲相続」という制度もあります。
法定相続人とは
法定相続人は、民法で定められた被相続人の配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などです。
相続の順位は以下の通りです。
- 第一順位 直系卑属(子どもや孫)
- 第二順位 直系尊属(親や祖父母)
- 第三順位 兄弟姉妹
これらの順位に従って、遺産が分割されます。
ただし、遺言書が存在する場合は、その内容に基づいた遺産分割をする必要があります。
代襲相続とは
代襲相続は、法定相続人が亡くなっている場合にその子どもや孫が相続権を引き継ぐ制度です。
例えば、被相続人の子が先に亡くなっていた場合、その子の子(孫)が代わりに相続人となります。
この制度により、故人の直系子孫が引き続き家族の財産を継承できるようになっています。
遺言書がある場合でも、法定相続人の遺留分(法律によって保護される最低限の相続分)の保証が存在するため、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。
法定相続分の割合は
法定相続分は、亡くなった方の遺産を法律に基づいて分配する際の、各相続人の取得割合を指します。
この割合は、相続人の関係性や順位によって異なります。
例えば、配偶者と子どもがいる場合、一般的に配偶者と子どもがそれぞれ半分ずつを受け取ることになります。
もし配偶者と両親が相続人の場合、配偶者が2/3、両親が1/3を分け合います。
これにより、法的な枠組み内で公平な資産の分配が保証されることを目的としています。
特に遺言がない場合、法定相続分に従って遺産分割が行われるので、トラブルが起きぬようしっかり把握しておきましょう。
相続財産の種類と対象
相続財産には、故人が所有していたプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)の2種類があります。
この区分は、相続手続きにおいて資産の評価や適切な管理が求められるため重要です。
また、特定の条件下で、一部の保険金や退職金は直接指定受取人に渡るため、通常の相続財産からは除外されます。相続税の計算にも重要になりますので、法的なトラブルを避けるためにも理解しておきましょう。
相続対象となる財産と非対象財産
相続財産に含まれるもの
相続財産は故人が亡くなった時点で保有していた全ての財産を含みます。
これには不動産、預貯金、株式、自動車などの有形資産だけでなく、著作権や特許などの知的財産も含まれます。
また、故人名義の借金や負債も相続財産に該当します。
相続財産に含まれないもの
特定の受取人が指定された生命保険金や退職金などは、故人が亡くなると直接指定された受取人に支払われるため、相続財産には含まれません。
また、故人の個人的な資格や権利、例えば弁護士の資格なども含まれません。
これらは他人に移転することができないため、相続の対象外となります。
プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)
プラスの相続財産(積極財産)の具体例
- 不動産(住宅、土地、ビルなど)
- 預金、株式、債券などの金融資産
- 自動車、船舶、オートバイなどの乗り物
- 家具、家電、ジュエリー、アート作品などの貴重品
- 特許権、著作権などの知的財産権
- 事業の株式やパートナーシップの持分
マイナスの相続財産(消極財産)の具体例
- 個人の借金やローンの残高
- 未払いの税金(所得税、固定資産税など)
- クレジットカードの支払い残高
- 法的紛争や訴訟に関連する費用
- 未払いの医療費
- 故人名義の商業貸倒れ
相続税の計算と申告
相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に発生します。
相続税申告は、相続発生を知ってから10ヶ月以内に行う必要があるため、発生する場合は適切に申告しましょう。
相続税の基礎控除額と課税対象財産の計算方法
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて異なります。
具体的には、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」と計算されます。
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円になります。
相続税は控除額を超える部分の財産に対して課税されることになります。
また、課税対象財産の計算には、不動産、金融資産など相続財産の評価が必要になります。
相続税申告の手続きと期限
相続税の申告手続きは、相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続人はこの期間内に、遺産の詳細なリスト作成、評価、および必要書類の準備を行い、税務署に申告を提出しなければなりません。
申告には、相続財産の評価書、遺産分割協議書などが必要で、適切な評価と正確な情報提供が求められます。
遅れると遅延税が課されることがあるため、申告は期限内に終わらせましょう。
まとめ 困ったら専門家へ相談を
相続は多くの手続きと複雑な知識が必要かつ、私的な感情が入り混じるため、あらゆるトラブルが起こりがち。
一見シンプルに思える相続でも、実際にはさまざまな問題が潜んでいることが少なくありません。
例えば、遺産分割が争いの原因となったり、税金の計算に頭を悩ませることも。
こうした状況をスムーズに乗り越えるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続に関わる専門家には、税理士、弁護士、公証人などがいます。
税理士は遺産の評価や税金の計算をサポートし、弁護士は遺産分割協議の調整や遺言の執行、法的な紛争の解決を手助けします。
また、公証人は遺言書の公正証書を作成する際に関与します。
相続はただの法的手続きではなく、故人の意志を尊重し、遺族間の絆を維持するための大切なプロセスです。
専門家の助けを借りながら、円滑かつ公平な遺産分割を目指しましょう。