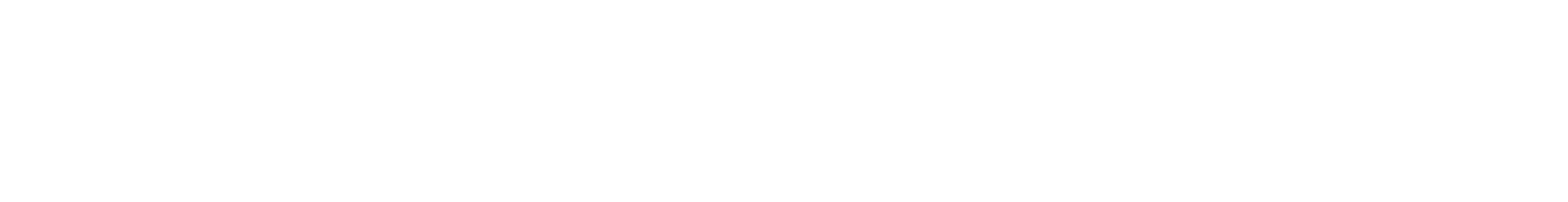相続放棄申述書とは、相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうための提出書類です。
この申述書を家庭裁判所に提出することで、相続放棄の審査が始まります。
相続放棄申述書には決まった書式があり、裁判所のホームページなどから入手ができます。
相続放棄申述書の提出期限
相続放棄申述書は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ提出する必要があります。この期間を過ぎると相続を単純承認したことになります。
ここで問題になるのが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつなのかということです。基本的には故人(被相続人)が亡くなった日と思っておいて問題ありません。ただし、被相続人の死亡後3か月以上経過した後に債権者からの問い合わせを受けて初めて被相続人に多額の借金があったことを知ったというようなケースでは、その借金の存在を知った日が3か月の起算日になります。
今からでも相続放棄申述手続きができるかどうか不安があるようなら、司法書士に相談しましょう。
相続放棄申述書の書き方
相続放棄申述書は相続を放棄するうえでとても重要な書類です。
相続放棄申述書と記入例は、最高裁判所の公式サイトからダウンロード・確認することができます。
以下、記入する項目について解説します。
- ・日付
-
書類の作成年月日を記入します。
- ・申述書を提出する裁判所
-
申述書を提出する家庭裁判所の名前を記入します。申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。最寄りの家庭裁判所というわけではないので注意してください。
- ・申述人の氏名
-
「申述人の記名押印」の欄を記入し押印します。印鑑は認印で問題ありません。この印鑑は後の手続きで使いますので、どの印鑑を押したかは覚えておきましょう。
住所や電話番号が間違っていると、裁判所から連絡がとれないので正確に書き込んでください。
電話番号については、携帯電話でも大丈夫です。昼間に通じやすい番号を書きましょう。 - ・法定代理人
-
申述人が未成年などの場合は、法定代理人等の欄を記入してください。
この場合、裁判所名の横の「申述人の記名押印」の欄も、法定代理人の氏名を記入、押印します。 - ・被相続人
-
被相続人の欄には、亡くなった人のことについて記入します。本籍と最後の住所、氏名、死亡年月日を書く必要があります。
本籍と最後の住所(亡くなった時に住民登録していた住所)は異なる場合もあるので気を付けてください。
本籍地は戸籍謄本、最後の住所地は住民票の除票と照らし合わせて、間違いないか確認しましょう。 - ・相続の開始を知った日
-
日付を書き入れ、1~4のうち当てはまるものを選んで、番号に丸をつけください。
相続放棄できるか否かに関わる重要な項目なので、間違えないように書きましょう。
同居の親族などであれば被相続人死亡の当日になる人が多いかと思います。遠方で暮らしていて縁がうすい場合、数週間後に知らされることもあるかもしれません。この際は、連絡をもらうなどで被相続人が亡くなったことを知った日を書いてください。 - ・放棄の理由
-
該当するものを選んで、番号を丸で囲みましょう。6のその他を選ぶ場合、〔〕に理由の記入が必要です。
- ・相続財産の概略
-
相続する遺産について書き入れます。負債についても記入する必要があります。
相続放棄申述書の手続きの流れ
書き終えた相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することで、相続放棄の審査が始まります。手続きは以下の流れで進めていきましょう。
漏れなく記入を終えた相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
提出する先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所なので、間違わないように注意してください。直接提出できない場合は、基本的に郵送でも受け付けてくれます。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、ケースにもよりますが1~2週間ほどで照会書が郵送されてきます。照会書に記載された質問項目への回答を、同封の回答書にまとめ、申述書に押した印鑑を押印して返送しましょう。
照会書の返送後、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が交付・郵送されます。
この書類で相続放棄されたことが証明できます。
照会書を返送する際のポイント
申述書を提出してしばらくすると家庭裁判所から「照会書」が届きます。相続放棄の申述が「本当に相続人の意思で行われたのか」などを確認するとても重要な書類です。照会書が届いたら質問への回答を記入し、家庭裁判所へ返送してください。
この回答によって相続放棄を認めるかどうかが決まります。申述書の内容と照会書の内容に齟齬があると相続放棄が認められないこともあり得ます。回答する際は、申述書の記載内容を踏まえ、十分注意して回答を記入しましょう。