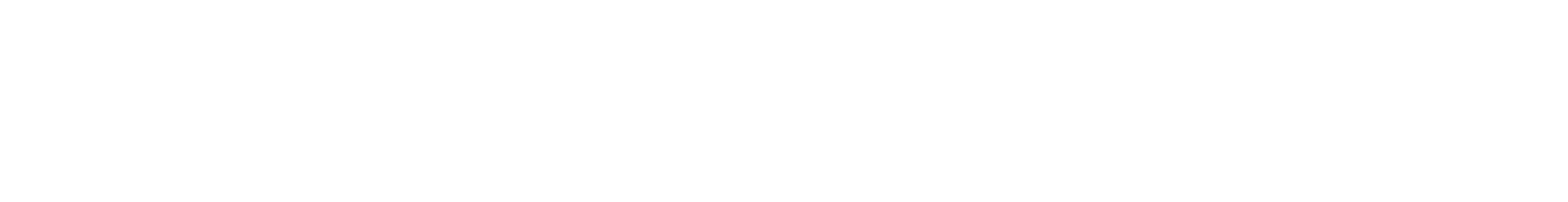法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。
簡単に言うと「相続関係が一目でわかる公的証明書」であり、法務局の登記官により証明されます。
この一覧図は平成29年5月から運用を開始した「法定相続情報証明制度」で扱われる証明書です。
運用当初、この証明書を使用できるのは登記申請のみでしたが、徐々に使用できる範囲が広がり、今では預貯金口座の名義変更・解約や相続税の申告における戸籍謄本の代わりとして使用できるようになっています。
もともと、法定相続情報証明制度は、所有者が亡くなったあとも相続登記が行われずに放置されている不動産が増加していたため、相続登記の促進を目的として運用が開始されました。
加えて、相続手続きにおける相続人の負担軽減もねらいのひとつです。
以前、相続人は戸籍謄本などの書類の束を手続き先ごとに提出する必要があり、大きな負担となっていました。
この制度により、最初に戸籍謄本等の束と一覧図を提出すれば、認証文が付いた写しが交付されます。
これを利用することで、その後の相続手続きでは戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。
法定相続情報一覧図が使える手続き
法定相続情報一覧図が使える手続きの場面としては、以下のようなものがあります。
・不動産の相続登記
・預貯金や有価証券の相続手続き
・自動車などの名義変更
・相続税の申告
・遺族年金、未支給年金等の年金手続き
法定相続情報一覧図のメリット
法定相続情報一覧図を取得する最大のメリットは、様々な相続手続きで戸籍謄本の束の代わりに使用できることです。戸籍謄本一式を何通も用意する必要がなくなり、手続きが効率化される、手続きに要する時間の削減にもつながります。
法定相続情報一覧図を取得できる人
一覧図は誰でも取得できるわけではありません。取得できる人物は、以下に限られます。
・法定相続人
・相続人から委任された民法上の親族
・相続人から委任された弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、弁理士
なお、法定相続情報一覧図は戸籍情報をもとに作成するため、被相続人および相続人が日本国籍を持っていない場合は、この制度は利用できません。
法定相続情報一覧図の取得費用・交付期間
申出や交付を受けるのに費用はかかりません。
ただし、郵送で行う場合は切手代がかかります。
申出から交付までの期間は1週間~10日ほどかかるケースが一般的ですが、早い場合は翌日に交付されるケースもあります。詳細は管轄の法務局に確認しましょう。
法定相続情報一覧図の有効期限
法定相続情報一覧図自体の有効期限はありません。
ただし、民間の会社や金融機関では独自に有効期限を設けている場合があるため、提出先に確認する必要があります。
また、法務局での保管期間は申出日の翌年から起算して5年なので、再交付する場合はその間が期限です。その間であれば、何度でも無料で再発行できます。
法定相続情報一覧図 取得までの流れ
法定相続情報一覧図を取得するには、まず必要書類と申出書を準備する必要があります。
まずは必要書類を準備します。
■必ず用意する書類
・被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(被相続人の本籍地である市区町村役場で取得 ※)
・被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地があった市区町村役場で取得)
・相続人の戸籍謄本または抄本(各相続人の本籍地である市区町村役場で取得 ※)
・申出人の氏名、住所が確認できる公的書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写しなど)
■必要となる可能性がある書類
・各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
・委任状(申出を委任する場合)
・申出人と代理人が親族関係にあることを証明する戸籍謄本(親族が代理の場合)
・資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(資格者代理人が代理の場合)
・被相続人の戸籍の附票(被相続人の住民票の除票が取得できない場合)
なお、戸籍謄本などの書類は返却してもらえますが、申出人の本人確認に使用した書類の写しなどは返却されません。
次に被相続人の戸籍と法務局の記載例をもとに、ご自身で元となる一覧図を作成します。作成における注意点は以下のとおりです。
・A4サイズの縦向きで記載し、用紙の下5㎝は空白にする(認証文が挿入されるため)
・手書きでもパソコン入力でも可(手書きでは、判読できるように明瞭に記載する)
・一覧図に記載する被相続人との続柄は、戸籍に記載されたとおりに記載する
・一覧図に各相続人の住所を記載するかは相続人の任意である
最後の住所記載については任意の項目となりますが、記載しておくと相続人の住民票の写しが不要となる機関もあります。
申出書に必要事項を記入し、準備した必要書類、作成した一覧図とともに申出を行います。申出する登記所は、以下の管轄の登記所から選ぶことができます。
・被相続の本籍地(亡くなった時点での本籍地)
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
上記の管轄登記所に行くことが難しい場合、郵送による申出も可能です。
その場合、郵送の切手代がかかるほか、返信用の封筒と切手を同封しなければなりません。