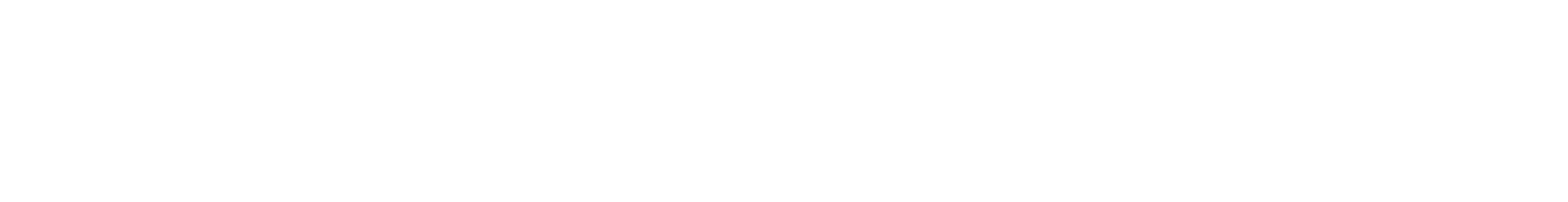不在者財産管理人とは、行方が分からず連絡がまったくとれない行方不明者(不在者)の財産を管理する人です。相続の場面では、行方不明の相続人に代わり財産を管理する人をさします。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人の1人が行方不明で連絡が取れない状況では遺産分割協議を行うことができません。
そこで、不在者財産管理人を選任してもらうことで、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加してもらい、全員同意で協議することで相続手続きを進められるようになります。
不在者財産管理人の申立て方法
不在者財産管理人は、不在者の配偶者などの利害関係者の申立てにより家庭裁判所で選任されます。
- 申立てできる人
-
利害関係人
- 申立先
-
不在者の最後の住所を管轄する家庭裁判所
- 費用
-
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(金額は各裁判所に要確認) - 必要書類
-
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍の附票
・財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票(推薦の場合)
・不在を証明する資料
・不在者の財産に関する資料
・申立人と不在者の利害関係を証明する資料 - 選任までの期間
-
数ヶ月~半年
家庭裁判所へ選任の申立てを行ったあと、家庭裁判所は不在者であるかどうかの審理を行います。この審理には数か月ほどを要し、不在者財産管理人の選任まで半年ほどの時間がかかることが通常です。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告と納税は死後10ヶ月以内に行わないと延滞税が課せられます。また、遺留分侵害額請求を行うためには1年以内の請求が必要です。
このような期限がある手続を行う場合には、速やかに不在者財産管理人を申立てましょう。
相続のタイミングで相続人の1人が行方不明のとき、行方不明となってから7年以上経っている場合には、不在者財産管理人ではなく、失踪宣告の申立てが可能です。
失踪宣告が認められると行方不明者は死亡扱いとなるため、その人の相続人と遺産分割協議を進めることができます。
※失踪宣告とは…行方がわからず一定の要件を満たした者を法律上、死亡したものとみなす制度
不在者財産管理人の役割
不在者財産管理人が担う役割は民法で定められている以下の3つです。
・不在者の財産を管理する
・不在者の財産目録を作成する
・家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を成立させる
不在者財産管理人は何でも自由に行えるわけではなく、家庭裁判所の許可が必要な行為があります。その場合は、権限外行為許可の申立て手続きが必要をすることになります。
不在者財産管理人の役割について詳しく見ていきましょう。
不在者の財産を管理する
不在者財産管理人の主な役割は不在者の財産を管理することです。
この役割は、不在者の所在が判明し財産を引き渡すまで続きます。
不在者財産管理人の権限は民法に定められています。
不在者財産管理人は権限の定めのない代理人に該当します。以下が民法の条文です。
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に揚げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
このように不在者財産管理人に認められている権限は、保存行為と管理行為(利用・改良)の2つです。
- 保存行為
-
財産の価値を保存し、現状を維持する行為
- 管理行為
-
財産の利用及び改良を目的とする行為
例えば、財産に賃貸不動産が含まれている場合、賃料の徴収や債務の返済を行います。
不動産の修繕が必要な場合も保存行為として対応します。
一方、「遺産分割協議を成立させる」「不動産を売却する」などの処分行為は保存行為や管理行為に該当しないため認められていません。家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議を成立させるなどの処分行為が可能となります。
不在者の財産目録を作成する
不在者財産管理人は選任後ただちに不在者の財産調査を行い、財産目録を作成し家庭裁判所に提出します。
不在者財産管理人の役割については、民法27条で以下のとおり定められています。
第27条(管理人の職務)
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は警察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
財産管理期間中は年に1回、財産の管理状況について家庭裁判所への報告が求められます。
家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を成立させる
不在者財産管理人の権限は、保存行為と管理行為の2つです。そのため、不在者の財産を勝手に処分することはできず、自身の判断で遺産分割協議を成立させることもできません。
しかし、家庭裁判所の許可があれば遺産分割協議を成立させることが可能となります。
第28条(管理人の権限)
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
ただし、家庭裁判所の許可は必ず得られるわけではないので注意が必要です。
許可の判断基準は、不在者が不当な不利益を受けず、処分行為が必要であることです。
遺産分割協議の成立を申し立てる場合、不在者のために最低限、法定相続分の確保が求められます。遺産分割協議の内容が不在者に不利だと判断された場合、遺産分割協議(案)の変更を要請されます。
そのため、不在者財産管理人が遺産分割協議を成立させるためには、不在者が正当に遺産を受け取れる遺産分割協議(案)を準備することが必要です。
権限外行為許可の申立て方法
遺産分割協議を成立させる申立ては以下のとおり行います。
- 申立てできる人
-
不在者財産管理人
- 申立先
-
不在者の最後の住所を管轄する家庭裁判所
- 費用
-
・収入印紙800円
・予納郵便切手 - 必要書類
-
・遺産分割協議書(案)
※その他、管轄家庭裁判所にて別途書類が必要とされる場合があります。
不在者財産管理人の選任が必要なケース
実際に不在者財産管理人の選任が必要なケースを具体的に紹介します。
・相続人の中に行方不明者がいて遺産分割協議が行えない場合
・行方不明の相続人に相続放棄をさせたい場合
・行方不明者との共同名義の不動産を売却したい場合
行方不明者が所有する財産は「本人かその法定代理人でないと対応ができない」のが原則です。そのため、行方不明者が相続人であった場合や行方不明者の財産の名義変更を行いたい場合、必ず不在者財産管理人の選任が必要となります。
具体的に不在者財産管理人が必要となるケースを把握し、ご自身の状況と照らし合わせて選任の要否を判断してください。必要な場合、急を要するケースもあるので注意しましょう。
相続人の中に行方不明者がいて遺産分割協議が行えない場合
ここまでお伝えしてきたとおり、相続人の中に行方不明者がいる場合は遺産分割協議を進めることはできません。
なぜなら、不在者にとって不当な遺産分割がなされたり、勝手に遺留分を放棄されるなど、不在者の不利益となる行為が行われる可能性があるからです。
そのため、遺産分割協議は相続人全員がそろった状態で行うことが必要となります。
そこで、不在者財産管理人を選任することで、不在者に代わって遺産分割協議を進めることができ、遺産相続をスムーズに行うことができます。
行方不明の相続人に相続放棄をさせたい場合
行方不明の相続人に相続放棄をさせたい場合は、不在者財産管理人を選任し家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
しかし、単に「遺産を渡したくないから」など、不在者の不利益になる事情では許可はおりません。被相続人の遺産の多くが負債である場合など、不在者の利益になる場合に相続放棄が認められます。
相続放棄ができるのは、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
相続人が行方不明の場合にも、当該行方不明者は自身のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。不在者が知らないうちに負債を負うということはありません。
例えば、相続人から1年後に突然連絡があり所在が判明、相続人はその際に被相続人の死亡を知ったという場合、そこから3ヶ月以内に申述すれば相続放棄が認められます。
その後、次の相続順位の人へ相続権が移ります。
しかし、そうすると相続人が確定しない状態が長期間続くことになります。
そこでこのような場合には行方不明の相続人の相続放棄を検討する必要があります。
行方不明者との共同名義の不動産を売却したい場合
『実家の名義が亡くなった父と行方不明の兄になっている』
被相続人の相続財産の調査を進める中でこのようなケースもあります。
その場合、実家を売却したいと考えていても勝手に売却することはできません。
このケースでも不在者財産管理人を選任することで不動産売却を進めることが可能です。
不在者財産管理人との話し合いのもと、共有名義の不動産全体の売却はもちろんですが、共有持分を買い取って共有名義を解消することも可能です。
もっとも、前述のとおり、家庭裁判所の許可を得るためには不在者の財産が不利益とならないことが必要です。
不在者財産管理人の選任方法
不在者財産管理人は、不在者の利害関係人の申立てによって家庭裁判所にて選任されます。自分たちで不在者財産管理人を自由に選ぶことはできません。
・不在者財産管理人を申立てる要件
・不在者財産管理人になる人
・不在者管理人が選任されるまでの流れ
ここでは、不在者財産管理人にはどのような人がどのように選任されるのか、この3つの要点で詳しく解説します。
不在者財産管理人を申立てる要件
不在者財産管理人の申立てをするには2つの要件を満たす必要があります。
- ①不在者であること
-
当然ながら、対象者が「不在者」でなければ不在者財産管理人の選任申立ては認められません。
裁判所のHPでは以下のように定義されています。不在者とは
従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)このように、容易に戻る見込みのない者となっているため、行方不明になって数か月程度では選任申立ては認められづらく、少なくとも数年以上の行方不明期間が必要です。
- ②財産管理人を置いていないこと
-
不在者が任意財産管理人を置いている場合、不在者財産管理人の選任申立てはできません。
任意財産管理人とは
財産管理委任契約の受任者のこと。
財産管理委任契約とは、事故や病気、加齢による判断能力の低下などによって財産の管理ができなくなる可場合に備え、親族や友人などの信頼できる人に財産の管理を委任する契約。不在者が任意財産管理人を置いている場合は、不在者の財産管理はもちろん、遺産分割協議にも任意財産管理人が参加します。そのため、不在者財産管理人を選任する必要がありません。
不在者財産管理人になる人
不在者財産管理人には特別な資格は不要です。しかし、不在者の財産を適切に管理すべく、財産管理の専門家である司法書士・弁護士が就任することが多いです。
不在者の財産を管理することが不在者財産管理人の役割です。
不在者の不利益とないよう、適格性が要求されるので、不在者財産管理人の選任は家庭裁判所に委ねられています。
自分たちで不在者財産管理人の候補者を推薦することは可能ですが、家庭裁判所が当該候補者を選任するとは限りません。
不在者財産管理人が選任されるまでの流れ
不在者財産管理人が選任されるまでの流れは以下のとおりです。
約1~4ヶ月
約3ヶ月~半年
不在者財産管理人の選任申立てを家庭裁判所へ行ってから、約1~4ヶ月かけて不在者の確認が行われます。
その後、選任をするかどうかの審判が行われ、不在者財産管理人が選任されます。
選任までの期間は約3ヶ月〜半年と長い期間が必要です。
そのため、遺産分割協議を急いで行いたい場合は速やかに申立てを行うようにしましょう。
不在者財産管理人を選任するのに必要な費用
不在者財産管理人を選任するために必要となる費用は以下の3つです。
申立て手続に必要となる費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(切手の金額は各裁判所に要確認)
不在者財産管理人が専門家となった場合の報酬
不在者財産管理人の報酬は、家庭裁判所が管理にかかる手間や難易度によって決定します。報酬の中には財産を管理するためにかかる手数料や経費なども含まれます。
この費用は、不在者の財産から支払われます。そのため、申立人が支払うことは基本的にはありません。
しかし、不在者の財産が少ない場合や負債しかない場合には不在者の財産から支払うことはできないため申立人が予納金を支払う必要があります。
予納金が必要な場合の費用
不在者の財産が少ない場合や負債しかない場合は、不在者の財産から不在者財産管理人の報酬等を支払うことができません。そのため、家庭裁判所は申立人に対し予納金の支払いを求めます。
予納金の金額については法律で定められていません。そのため、裁判所が以下の流れで決定します。
- 予納金の決定方法
-
①財産管理に必要な金額を算出(報酬+事務手数料)
②不在者の預貯金等の財産を確認
③足りない分を予納金として算定
予納金の相場は、20万円〜100万円です。
この予納金は、不在者の財産管理が終了した際、残っていれば返還されます。
しかし、予納金が残っていない場合は返還されないので注意しましょう。
予納金が高額な場合は申立ての取り下げもできるがリスクがある
予納金が確定するのは、不在者財産管理人の選任申立てを行った後です。
申立てをする際に予納金が発生する可能性があり、100万円ほど準備する必要があることを考えておくと良いでしょう。
しかし、遺産が20万円程度なのに予納金が100万円必要となったらどうでしょうか。
それなら、不在者財産管理人の選任はしたくないと思いますよね。
既に申し立て済みであっても、不在者財産管理人の選任申立てを取り下げることも可能です。
ただし、行方不明者がおり、その管理人もいない状況では遺産分割協議を進めることができないので、遺産はそのままとなります。これによるリスクが生じますので注意が必要です。