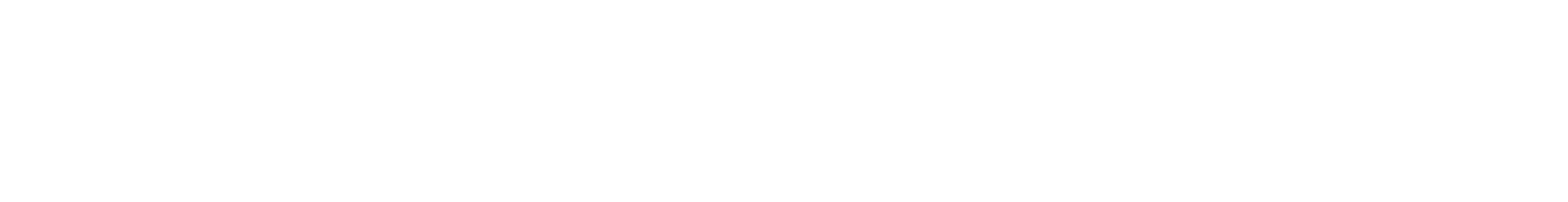相続は被相続人が亡くなることで発生しますが、生前贈与とは存命中に贈与することをいいます。
また、生前贈与では、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能です。
例えば、孫に財産を残したい場合は、遺言書に孫への相続について記載する以外にも、生前贈与という選択肢が考えられます。
贈与を受けたら贈与税の支払いが必要
贈与を行なった場合、受贈者(贈与を受ける人)は贈与税を支払う必要があります。
ただし、一定の条件を満たせば控除を受けられたり、贈与税が非課税になったりする場合もあり、税負担を軽減することが可能です。
なお、控除額を超えて贈与を行なった場合は、控除額から超えた分の金額について贈与税が課税されます。
生前贈与で税負担を軽減できる可能性がある場合
生前贈与は、一定の控除額や非課税制度を活用することで税負担を軽減できることもあるため、下記にあてはまる場合は生前贈与を検討してみてもよいでしょう。また、生前贈与であれば、受贈者が必要とするタイミングで財産を引き継ぐことができ、受贈者にも喜ばれるかもしれません。
なお、相続開始前7年以内に被相続人から贈与された財産は、生前贈与加算として相続税の課税対象となります。
- 贈与者の財産に余裕がある
- 相続人に引き継ぐ財産がすでに決まっている
- 受贈者が多い
- 受贈者が必要とするタイミングで財産を引き継ぎたい
※生前贈与加算は、相続人や受遺者が対象とされていますので、被相続人から相続財産を取得していない孫や子どもの配偶者への生前贈与は、原則として生前贈与加算の対象となりません。
生前贈与のメリット
生前贈与のメリットを3つご紹介します。
贈与する相手とタイミングを選べる
生前贈与は相続とは異なり、財産を贈与する相手とタイミングを自由に選べます。
遺言でも財産を贈与する相手を指定できますが、生前贈与は自分で実行するため確実に財産を贈与することが可能です。また、贈与のタイミングを選べば、必要なときに必要な金額を贈与することが可能です。
贈与税の負担を軽減できる制度がある
通常、贈与をすれば贈与税がかかりますが、控除や非課税制度を活用すれば贈与税の負担を軽減することができます。
贈与税の負担を軽減できる制度
生前贈与の控除と非課税について、その制度を5つご紹介します。
【制度1】暦年課税制度は基礎控除110万円まで非課税
「暦年課税」とは、1年間の贈与額に応じて課税される課税方式です。暦年課税には基礎控除が設けられており、1月1日から12月31日までの1年間の贈与に対して、受贈者1人あたり110万円が控除されます。贈与額が110万円を超えた場合には、超えた部分の金額が贈与税の課税対象となります。
なお、相続人や受遺者が相続開始前に被相続人から贈与された財産は、贈与時期の違いにより次のとおり生前贈与加算として相続税の課税対象となります。この場合、110万円の控除の範囲内の贈与であっても加算対象となります。
【制度2】相続時精算課税制度は贈与額2,500万円プラス基礎控除110万円まで非課税
生前贈与を行なうにあたっては、「相続時精算課税制度」を利用するという選択肢もあります。相続時精算課税制度においては、贈与額2,500万円までは贈与税が課税されず、2,500万円を超えた部分は20%の贈与税が課される制度です。
ただし、この制度を利用して贈与した財産は、すべて相続税の対象となることに注意しましょう。なお、2,500万円を超えて課税された贈与税は、相続税から控除されます。
2024年1月1日以後の贈与から、特別控除額2,500万円に加え毎年110万円までの基礎控除が設けられ、①110万円までの基礎控除は、その金額までの贈与であれば相続時精算課税制度を選択していても贈与税の申告は不要とされ、②贈与税が課税される2,500万円の限度額計算に含まれず、③相続税の計算の際に加算不要です。
相続時精算課税制度の対象は、60歳以上の父母・祖父母から18歳(2022年3月31日以前は20歳)以上の子どもや孫に対しての生前贈与です。相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書などを税務署に提出する必要があります。
【制度3】夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」とは、夫婦間で居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合に、暦年課税の基礎控除である110万円に加えて、最高2,000万円まで控除されるという制度です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与に適用されることから「おしどり贈与」とも呼ばれます。適用を受けるためには、下記の要件を満たし、贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する必要があります。
- 居住用不動産または居住用不動産を購入するための資金の贈与
- 婚姻期間が20年以上の夫婦
- 同一の夫婦間で初めての利用
- 贈与の翌年3月15日までに贈与を行った不動産または贈与資金で購入した不動産に住んでおり、将来も住み続ける意思がある
【制度4】祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」は、令和8年3月31日までにおいて、子どもや孫などの直系卑属に対して教育資金を贈与した場合、1,500万円までの一括贈与が非課税になるという制度です。受贈者が30歳になるまで適用されます。
ただし、学校教育法上の教育施設や外国の教育施設以外に直接支払う費用の非課税は、そのうちの500万円が限度です。
なお、非課税限度額内であれば何度でも追加で贈与が可能ですが、超えた場合はその部分の金額が贈与税の課税対象となります。また、教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、条件によっては管理残額を贈与者から相続などにより取得したものとみなして課税対象になることも注意しましょう。
【制度5】直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」とは、令和9年3月31日までにおいて、直系尊属である父母・祖父母から子どもや孫などへ結婚・子育て資金を贈与した場合、贈与税が非課税になる制度です。
非課税限度額は受贈者1人あたり1,000万円までですが、そのうち結婚資金は300万円が上限となっています。なお、受贈者である子どもや孫は、18歳以上50歳未満であることが条件です。
生前贈与の活用を検討するケースとは
ここまで生前贈与のメリットなどをご紹介しましたが、続いて生前贈与の活用を検討するケースをご紹介します。生前贈与をするかどうかの判断の参考にしてください。
特定の人に贈与したい
相続では、民法により財産を承継する相手(法定相続人)と承継する割合(法定相続分)が決められています。遺言で特定の人に多くの財産を承継することはできますが、遺留分侵害額請求など分割内容を不服とする相続人がいた場合に相続人同士でトラブルになることも懸念されます。
生前贈与は、財産を贈与する相手や金額を自由に決めることができます。特定の人に特定の財産を承継したいのであれば、生前贈与も選択肢の一つになるでしょう。
必要なときに贈与したい
相続は、財産を承継する人の死亡によって発生します。一方、生前贈与は相続の開始を待つことなく財産を承継することが可能です。子どもや孫の進学、マイホームの購入など、お金が必要なときに必要な金額を贈与することが可能です。
贈与相手が若い
贈与する相手が若い場合も、生前贈与の活用を検討できます。
生前贈与で暦年課税の基礎控除を利用する場合は110万円以下の贈与は非課税です。贈与する相手が若ければ、時間をかけて多額の贈与をすることが可能です。
また、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた受贈者が18歳以上である場合には、一般税率よりも税率構造が緩和された特例税率を適用できます。
相続トラブルが懸念される
将来相続が発生した際、財産の分割をめぐり相続人同士のトラブルが懸念される場合は、トラブルのもとになりそうな財産を生前贈与してトラブルを回避することも一つの方法です。
生前贈与では、例えば、自宅を配偶者に贈与して現預金を子どもたちに贈与するといったことを、自分で決めて実行することができます。
財産は少ないが遺言による承継が不安である
被相続人の財産が基礎控除以下の場合は相続税がかかりません。基礎控除額は相続人の数により変動し、相続人が1人の場合は3,600万円です。これより財産が少ないようであれば、相続税の計算上、生前贈与を行なうメリットはありません。
ただし、財産を贈与したい人や贈与する目的が決まっているものの、遺言で財産を承継させることに不安がある場合は、生前贈与を検討するとよいでしょう。
生前贈与を行なう際の注意点
生前贈与を行うにあたっては、親族間でのトラブルの原因とならないよう注意したいものです。続いては、生前贈与を行なう際の注意点についてご紹介します。
受贈者以外にもできるだけ納得してもらえる贈与を
生前贈与で注意したいのは、受贈者以外の親族にもできるだけ納得してもらえる贈与にしたほうがよいということです。何の説明もなく特定の受贈者に多額の贈与を行なった場合、後にトラブルを引き起こす原因となる可能性があります。受贈者以外の親族にも生前贈与の理由や相続についての考え方を伝えておくとよいでしょう。
遺留分に注意する
遺留分とは、法定相続人に法律で認められた最低限の相続分のことをいい、相続時に遺留分を主張することができるのは、被相続人の配偶者と子どもおよび子どもが死亡していた場合に代わって相続人となる孫などの代襲者、父母などの直系尊属です。特定の相続人に対しての贈与が多額だった場合などは、その贈与が遺留分を侵害しているとして、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
生前贈与を行なう際には、相続人となる人に対しての遺留分にも配慮しましょう。
なお、遺留分算定の基礎となる金額には、相続発生時の財産のほか、下記条件に当てはまる場合は、被相続人が生前に贈与した財産も対象になります。
- 相続開始前1年以内に行なわれた相続人以外への贈与
- 相続開始前10年以内に行なわれた相続人への贈与
- 遺留分を侵害すると知りながら行なわれた贈与
定期贈与とみなされると贈与税が課税される
暦年課税の基礎控除である110万円の範囲で贈与をしていたとしても、定期贈与とみなされて贈与税が課税される場合があります。
定期贈与とは、あらかじめ一定額の財産を贈与することを約束していて、それを定期的に分割して贈与することです。例えば、1,000万円を贈与する約束で、毎年100万円ずつ10年にわたって贈与した場合は、定期贈与とみなされます。定期贈与とみなされれば1,000万円から基礎控除110万円を控除した890万円に対して贈与税が課税されます。
贈与者と受贈者との間で贈与を行なう都度、贈与契約書を作成するなど、定期贈与とみなされないよう注意しましょう。
相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象になる
相続人や受遺者が相続開始前に被相続人から贈与された財産は、贈与時期の違いにより次のとおり生前贈与加算として相続税の課税対象となります。この場合、110万円の控除の範囲内の贈与であっても加算対象となります。
よって、相続税の課税対象になる財産を少なくする目的で生前贈与をしても、贈与者の相続開始前の贈与は対策の効果がなくなってしまいます。 なお、生前贈与の際に贈与税を納税している場合は、その税額を相続税額から控除することができます。
なお、次の贈与については相続開始前の贈与であっても相続財産に加算されません。
- 相続や遺贈により財産を取得していない人への贈与
- 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を適用した贈与
- 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例で非課税と認められた金額
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例で非課税と認められた金額
特別受益として相続の対象に持ち戻されることがある
共同相続人の中に被相続人から生前贈与などの特別の利益を受けた人がいる場合、相続人間の不公平を是正するため、この特別の利益を特別受益として相続財産に持ち戻す制度があります。
各相続人の相続分を計算するときは、相続発生時において有した財産の価額に特別受益にあたる贈与の価額を加えます。特別受益にあたる生前贈与を受けた人は、特別受益を加えて計算した相続分から特別受益を除いた額の財産を受け取ります。
生前贈与が特別受益として相続財産に持ち戻されるケースは、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた場合です。
つまり、婚姻や養子縁組の際の持参金や開業資金、住宅購入資金などが該当し、通常の扶養の範囲に含まれるものは該当しません。
なお、被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をした場合は持ち戻しの対象になりません(ただし、前記遺留分の制約は受けます)。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与についても持ち戻しの対象になりません。